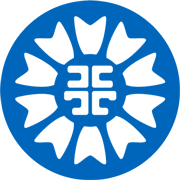農地転用<資材置き場> 第6回最終回 資材置き場をつくるときの造成・舗装工事と開発許可

こんにちは、行政書士ライフ法務プランニングの大場です。
本日で農地転用<資材置き場>ブログシリーズの最終回となります
第6回最終回は 資材置き場をつくるときの造成・舗装工事と開発許可についてです。
前回のブログはコチラ⇒第5回|資材置き場の無断転用リスクと農地転用(追認)申請
それでは、始めていきましょう。
農地を資材置き場に転用するとき、単に「農地転用許可」を取れば安心…と思われがちですが、実際には
造成工事や舗装工事に伴って「開発許可」が必要になるケース があります。
特に建設会社や工務店が自社で資材置き場を整備するときに注意すべきポイントを整理します。
1. 資材置き場と造成・舗装工事の関係
資材置き場をつくるとき、多くの場合は農地をそのままでは使えません。
これらの工事を伴うと、農地法のほかに 都市計画法上の「開発行為」 に当たる可能性があります。
ただし、単なる砂利敷き・整地程度で、大規模造成と判断されない場合は除きます。
2,法的根拠
「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。
※「都市計画区域外」で資材置き場をつくる場合は、都市計画法による「開発許可」の規制が及びません。
3. 「開発行為」にあたるかどうか
小規模(1,000㎡未満)の資材置き場なら原則として開発許可は不要ですが、市町村によっては 条例やガイドラインでより厳しい規制があるので要注意です。
4. 宮城県内での実務上の注意点
特に令和5年に施行された「盛土規制法」により、一定規模以上の盛土・造成を行う場合は追加の許可や届出が必要になることがあります。
5. 無許可で工事を進めた場合のリスク
ご相談は無料です。
お問い合わせ・ご相談予約はコチラ⇒お問い合わせフォーム
農地転用(資材置き場)|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山