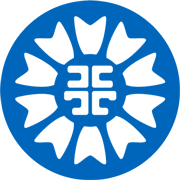「農業を始めたい人が知らない“許可”の壁」シリーズ④<全5回>

こんにちは、行政書士ライフ法務プランニングの大場です。
本日は、「農業を始めたい人が知らない“許可”の壁」シリーズ④です。
テーマは営農計画が甘いとNG? 許可される計画のつくり方です。
それでは、始めて行きましょう。
許可される営農計画書のつくり方
「農業はやってみないと分からない」は通用しない
農業を始めようとすると、最初にぶつかる壁のひとつが「営農計画を出してください」という要求です。
「とりあえずやってみてから考えたい」「細かい数字まではまだ…」
そう思う方も多いですが、農地を借りる・買うには、現実的な営農計画を作ることが許可の条件になっています。
営農計画が必要な理由
農業委員会が審査で見るのは「この人は農地をきちんと活用できるか?」という視点です。
つまり、
・農地が荒れたまま放置されないか?
・継続して農業を続けられる体制があるか?
それを判断するために「計画の中身」が問われるのです。
甘い営農計画によくある3つのNGパターン
❌ 1. 売上や経費に根拠がない
例:「年間300万円売れると思う」→ 単価も収量も不明
❌ 2. 作付内容が曖昧
例:「野菜をいろいろ育てる予定」→ 何をどれだけ、の記載がない
❌ 3. 販路や販売方法が不明確
例:「SNSなどで販売したい」→ 誰に?どのくらい?が説明できない
※販売目的ではなく自家消費の場合は販路や販売方法は不要な場合あり
許可される営農計画のポイント
<作業体制が明確>
※販売目的ではなく自家消費の場合は販路や販売方法は不要な場合あり
< リスク対策を考えている>
「認定新規就農者制度」の計画様式の活用
多くの自治体では「認定新規就農者制度」に申請する際、営農計画のフォーマット(青年等就農計画)が用意されています。
この書式に沿って考えると、農業委員会に通るレベルの計画が整理できます。
不安なときは誰かと一緒に作るのが近道
計画づくりは、一人で抱え込むよりも
・JAの営農指導員
・ 市町村の農業振興課
・ 認定農業者や地元の先輩農家
・ 行政書士などの専門家(新規就農や農地に詳しい行政書士に限る)
などと相談しながら進めるのがおすすめです。
“営農計画=夢の設計図”
次回予告
次回→農業を「始められる人」と「始められない人」の違い? についてお伝えします。