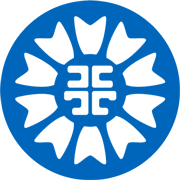「農業を始めたい人が知らない“許可”の壁」シリーズ③<全5回>

こんにちは、行政書士ライフ法務プランニングの大場です。
本日は、「農業を始めたい人が知らない“許可”の壁」シリーズ③です。
テーマは農業経験ゼロでも大丈夫? 許可が取れる人・取れない人の違いです。
それでは、始めて行きましょう。
「農業未経験だけど、やる気はある!」は通用する?
「農業経験はないけれど、田舎に移住して畑をやりたい」
「家庭菜園くらいしかしたことがないけれど、本気でやってみたい」
こうした想いを持つ就農希望者の相談はとても多いですが
現実には、やる気だけでは農地の“許可”はおりないケースもあります。
では、何が違いを分けるのでしょうか?
「農業経験がないとダメ」ではない
まず大前提として、
農業経験ゼロでも農地の貸借・取得は可能です。
ただし、農業委員会が重視するのは「農業経験」そのものより、“営農計画の実現可能性”と“農業への本気度”です。
許可が取れる人の共通点
農業委員会が安心して許可を出せる人には、次のような特徴があります:
① 具体的な営農計画を持っている
●収支や販売先の見込みまで考えている。
② 農業研修や実習を受けている
③ 地域の農家・支援機関とつながっている
④ 常時従事できる体制を確保している
許可が下りにくい人の特徴
一方で、許可が難航するケースでは以下のような傾向があります:
❌「やってみたい」だけで具体性がない
→「何を育てたいかはこれから決める」はNG
❌ 営農計画が曖昧・甘い
→「収支が赤字でも自己資金でなんとかなる」は通りづらい
❌ 研修・現地視察をしていない
→机上の空論と思われると、信頼されにくい
❌ 地元とのつながりが薄い
→農地貸主が不安を感じ、話が進まないケースも
農業経験を補う“準備”とは?
(「認定新規就農者制度」の活用にもつながる)
→ 実地調査・面談・農家訪問などでの行動履歴が信頼材料に
→ 作付け・収支・販路・自己資金・作業体制を明確に
→ JA・地域の農業振興課・農地中間管理機構など
“経験ゼロ”でも、行動がすべて
次回予告
次回→ 営農計画が甘いとNG?許可される計画の作り方についてお伝えいたします。