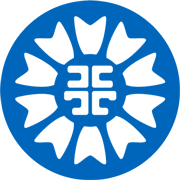「農地を借りて野菜づくりをしたい」は簡単じゃない?
就農を考える多くの人が最初にぶつかる壁。
それが、「農地を借りるには許可がいる」という事実です。
空いている農地を見つけたとしても、地主さんの「いいよ」というひと言だけでは始められません。
農業委員会の許可=“農地法第3条の許可”が必要なのです。
農地法第3条って、そもそも何?
じゃあ、どうすれば借りられるの?
農業委員会が第3条の許可を出すためには、以下の4つの条件をすべて満たす必要があります。
① 全部効率利用要件
借りる農地をすべて耕作に使うことが求められます。
例:広すぎて手が回らない/一部だけ使いたい → NGになる可能性も。
② 常時従事要件
申請者または同居家族などが年間150日以上、農業に従事できること。
例:週末だけの家庭菜園ではNG。
会社を続けながらの兼業は、“実態”によって判断されます。
③ 地域との調和要件
水利の管理、農道の利用、作物の選定など、周辺農業に支障を与えないこと。
地域の農業者との“すり合わせ”ができていないと許可が難航することも。
④(法人の場合)農地所有適格法人であること
法人が農地を買う場合は、「農地所有適格法人」である必要があります。
※<令和5年の法改正で「下限面積要件」は撤廃>
小さな面積で、家庭農園+直売所のような事業も選択肢に。
許可が通る・通らないの境界線とは?
農業委員会が見るのは、「この人、本当に農業できるのか?」という“実行可能性”です。
許可されやすいケース
❌ 許可されにくいケース
まずは「農業委員会」に相談しよう
農地法第3条の許可は、農業委員会の判断がすべてです。
地域によっては、農業支援センターやJAとの連携も必要な場合があります。
事前相談ではこんな資料があるとスムーズ
農地を借りるには“準備”がすべて
次回予告
次回→農業経験ゼロでも大丈夫?許可が取れる人・取れない人の違いについてお伝えいたします。