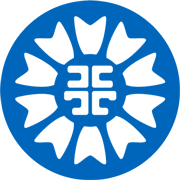「農業を始めたい人が知らない“許可”の壁」シリーズ①<全5回>

こんにちは、行政書士ライフ法務プランニングの大場です。
本日は、「農業を始めたい人が知らない“許可”の壁」シリーズ①です。
テーマは農地があっても始められない?です。
それでは、始めて行きましょう。
「農地がある=すぐ農業できる」は間違い?
「親から農地を相続したから、これを使って農業を始めたい」
「空き農地が見つかったから借りて野菜を作ってみたい」
そんな思いを持つ就農希望者は多いものの、実は“農地があるだけ”では農業を始められません。
なぜなら、農地を取得したり借りたりするには、「農地法」という法律に基づいた“許可”が必要だからです。
農地を使うには“農地法の許可”が必要
就農する際、最も基本となるのが農地法第3条です。
これは「農地を耕作目的で取得したり借りたりするには、農業委員会の許可が必要」というルール。
この許可を受けないまま農地を利用すると、違法な状態となり、行政から是正措置を求められることも。
つまり、農地があっても「勝手に使ってはいけない」ということです。
許可には“条件”がある
農業委員会が許可を出すには、以下の条件をクリアする必要があります。
① 全部効率利用要件
取得・借用する農地をすべて耕作に使うこと。
② 常時従事要件
本人または世帯員が年間150日以上、農業に従事できる体制があること。
③ 周辺との調和要件
農業用水の管理や営農形態など、地域の農業に悪影響を与えないこと。
④ 法人要件(法人の場合)
農地を取得する法人は「農地所有適格法人」である必要があります。
「親の土地」でも自由には使えない?
よくある誤解がこちらです
「親の名義だから、許可はいらないでしょ?」
→ 名義が親であっても、自分が耕作を始めるなら“借りる”扱いになり、許可が必要です。
また、相続後に農業を始める場合も、農業委員会への届出や手続きが必要になることがあります。
農業は“始める前”が大事
農地があっても、気持ちだけでは始められないのが農業です。
就農には、法律・制度・地域との関係性をきちんと理解することが欠かせません。
農地はあっても「許可」がないと始められない
●農地法第3条に基づき、農地を借りる・買うには許可が必要です。
●下限面積の撤廃でハードルは下がったが、他の要件は依然厳格
●「農業をやりたい」という思いを形にするには、計画性と手続きがカギです。
※「下限面積」制度は廃止されました。
かつては「50アール以上ないと農地を取得できない」といった**“下限面積”の制限**がありましたが、
令和5年4月1日の法改正により、全国一律で撤廃されました。
つまり、現在は面積の大小に関係なく、農地取得・貸借の申請が可能です。
ただし、面積の要件がなくなっても、「誰でも自由に使える」わけではありません。
次回予告
次回→農地は借りれる?農地法3条のハードルについてお伝えします。