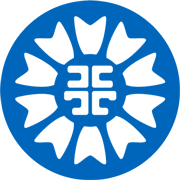農業委員会への申請ってどんな感じ?【農地法5条申請の現場】
![PXL_20250707_050350277[1]](/materials/175189203842101.jpg)
こんにちは、行政書士ライフ法務プランニングの大場です。
本日は、農業委員会への申請ってどんな感じ?【農地法5条申請の現場】というテーマでお伝えします。
それでは、はじめていきましょう。
「農地転用って、何から始めればいいの?」
農地を駐車場や資材置場にしたい、あるいは家を建てたい──
そんなときに必要になるのが農地法5条申請です。
でも実際、「どこに行けばいいの?」「申請って何をするの?」と不安に感じる方も多いはず。
今回は、農業委員会へ実際に申請に行った現場の様子と流れを、行政書士の視点でお伝えします。
農業委員会は“地域ごとの窓口”
農地法5条申請の受付窓口は、市町村の農業委員会。
市役所や町役場の一角に設置されていることが多く、「農業委員会事務局」などの看板が目印です。
☑ 事前相談がスタートライン
申請前に、まずは農業委員会で事前相談を行います。
ここで確認すること
●その土地が本当に転用できるか
●必要な書類の種類
●次の委員会の開催日(許可がいつ下りるかの目安)
行政書士として現場に行くと、担当者が図面や公図を広げて「ここは農振除外が必要ですね」などと具体的な指摘をくれることが多いです。
実際の申請現場の様子
農業委員会の窓口は、決して堅苦しい雰囲気ではありません。
職員さんも「地域の土地をどう使うか」を大切に考えているので、相談に親身に乗ってくれます。
現場でよくある会話
「申請書は一通りそろっていますか?」
「位置図の縮尺を○○に直してください」
「断面図が必要ですので、何日までそろえてください」
「利用計画図はありますか?」
「排水はどうしますか?」
「隣接者の同意はもらっていますか?」
「求積図が必要です。」
「造成工事はいくらかかりますか?」
「工事費は自己資金ですか?、銀行借り入れですか?」
「次回の委員会は○月○日です。それまでに現地確認が入ります。」
行政書士が代理で事前相談に行く場合、その場で不備を調整したり、追加資料を確認できるので、スムーズに手続きに入れます。
知っておきたいポイント
● 農地法5条申請は、毎月の締切日がある
→ 定例会で審査されるため、締切を逃すと1ヶ月遅れることも。
● 市町村ごとにローカルルールがある
→ 「隣接道路の幅員証明」など、地域独自の添付書類が必要な場合も。
● 許可までの期間は申請から1か月半が目安
→ 余裕をもったスケジュールで。
行政書士として感じること
私が現場で感じるのは、「事前相談の重要性」です。
ここでの確認を怠ると、**提出後に“やり直し”**になりがちです。
初めての方には難しく感じる書類作成や調整も、行政書士に任せることでスムーズに進みます。
安心して進めるために
農業委員会への申請は、思ったより身近な手続きです。
ただし、申請書類の正確さやスケジュール管理がカギ。
✅ 「この土地、転用できるかな?」
✅ 「何から始めればいい?」
そんな時はお気軽に当事務所に相談ください。行政書士として、事前相談の段階からお手伝いします。
無料相談受付中
農地法5条申請サポート
👉 [詳しくはこちら]
宮城県の農地転用手続きサポート|行政書士事務所ライフ法務プランニング
対応エリア:宮城県内