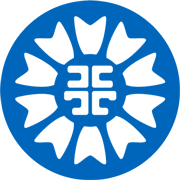「道具がない、技術がない」<第1章④きっかけと出会い>

こんにちは、行政書士ライフ法務プランニングの大場です。
行政書士が関わった移住者×就農ストーリー《第1章から第4章までのブログシリーズ》の第4回目は「道具がない、技術がない」<第1章④きっかけと出会い>というテーマでお伝えします。
前回までのお話はこちら⇨農業を始めるための最初の“壁”<第1章③きっかけと出会い>
それでは、始めて行きましょう。
農地法の許可も下り、ようやく“自分の畑”ができた関さん。
しかし、本当の意味でのスタートは、そこからでした。
「いざ畑に立ってみたら、何をどうすればいいのか、まったく分かりません。」
農地を“持っている”ことと、“活かせる”ことの間には、大きなギャップがあります。
最初の関さんは、道具も、知識も、経験もゼロ。
それでも、彼は一歩ずつ、自分の畑を耕し始めたのです。
道具がない。「まず、何が必要かも分からなかった」
移住したての関さんは、農具を一つも持っていませんでした。
・鍬(くわ)って種類があるの?
・耕運機と管理機の違いは? どちらを購入すればいいの?
・土つくりはどうすればいいの?
最初にぶつかったのは、「道具の選び方が分からない」という壁でした。
そこで、私は大崎農業改良普及センターや先輩農家の紹介を通じて
・農機具を貸してくれる農家さん
・初心者向けの家庭菜園サイズで始める方法
・畑の土壌調査をしてくれる機関(JA)
などを一緒に調べました。
技術がない。「畝の立て方をYouTubeで調べてました」
農作業の基本である“畝立て”。
しかし関さんは「“うね”って何?」というレベルからのスタート。
今の時代、動画で調べれば出てきます。
でも、地域によって土質も水はけも違うので、本当に役立つのは“近くの人のやり方”です。
そこで2人で近所のベテラン農家さんに声をかけ教えてもらうことにしました。
その結果・・・
「自分一人で悩むより、“聞いたほうが早い”って初めて分かりました」
と関さんが笑ったのを覚えています。
“始められる畑”と“続けられる畑”は違う
関さんは、小さな面積から野菜づくりを始め、現在は、畑の範囲も大きくなりいろいろな種類を育てることに成功しています。
草刈りのリズム、水やりのコツ、土が硬い時の工夫——
どれも実際にやってみて、体で覚えていくしかありません。
行政書士である私のサポートは、ここまで来ると“制度”から“関係性”へ。
●地域の助けが得られるようなつなぎ役
●相談できる体制をつくること
こうした「しくみと人をつなぐ役割」が、地味ですがとても大事だと感じています。
あとは、関さんの明るいキャラクターと人懐こい性格でどんどん農家の知り合いができて素直さもあり信頼関係を築き、今では一緒に渓流釣りに行ったり、山菜採りにいくような関係性が出来上がっています。
この地域の人たちは(宮城県大崎市岩出山) 東京から移住してきた新規就農者には優しいということがわかりました。
関さんは東京に住んでいた頃と違って毎日が充実していて地域のあったかさを感じているようです。
「やったことがない」から始める人を、応援したい
関さんは、いまも「まだまだ分からないことばかりです」と言います。
でもその姿勢が、地域の人からも少しずつ信頼を得てきています。
「道具も技術もなかったけれど、“やりたい”気持ちがあれば何とかなるんですね」
この言葉は、これから農業に挑戦したい人すべてへのエールになると思っています。
次回
第5回:「最初の野菜が芽を出した日」——“育つ”喜びと小さな達成感
新規就農のご相談はコチラ⇨行政書士事務所ライフ法務プランニング