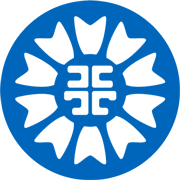新規就農者のための「農地法第3条」まるわかり第一回目(全4回)

こんにちは、行政書士ライフ法務プランニングの大場です。
本日は、新規就農者のための「農地法第3条」まるわかり 第一回というテーマでお伝えします。
それでは、始めて行きましょう。
「農地を買いたい・借りたい」だけじゃダメ?“農地法第3条”って何?
「農業を始めたい」「農地を買いたい」「貸してもらえる話がある」そんなふうに、新たに就農を目指す方からよく相談を受けます。
でも、最初に必ずお伝えしているのが──
🌾 農地は、勝手に売ったり借りたりできないということ。
これは農地を特別に守る法律「農地法」があるためです。
そもそも「農地法」って?
農地法とは、簡単に言えば
➡ 農地を守るための法律です。
食料の安定供給のためには、農地が安易に宅地や駐車場に変えられてしまっては困りますよね。
そのため、農地を「誰がどう使うか」について国がコントロールしているのです。
第3条は“農地を農地として使う人”のための許可制度
農地法の中でも「第3条」は、農地を“耕作目的で”取得したい人が必要となる許可です。
つまり、「農地を農地として使う」場合であっても──
✅ 買う(所有権を移す)
✅ 借りる(賃貸借契約する)
いずれも 農業委員会の許可が必要になります。
農業をやる気があるのに、なぜ許可がいるの?
実際に耕作する人かどうか、継続的に農業を行えるかどうか、農業委員会がチェックする仕組みなのです。
相続した場合は許可はいらない?
相続など「権利の移転」が法律上自動的に起きる場合は、第3条の許可は不要です。
ただし、市町村への「届出」は必要になります。
許可の窓口はどこ?
各市町村にある「農業委員会」が窓口です。
多くの地域では月1回の審査会で申請を審査し、許可を出しています。
就農の第一歩は「第3条の壁」を知ることから
「土地の持ち主が貸してくれると言っているから、大丈夫」──そう思って契約してしまうと、あとで無効になってしまうこともあります。
新規就農を考えている方は、農地法第3条のしくみと、地域のルールを早めに知ることが大切です。
そして、わからないときは早めに相談できる専門家(行政書士など)と一緒に進めるのがおすすめです。
次回は
「就農希望者が見落としがちな“許可の条件”とは?」**について、具体的にご紹介していきます!
お問い合わせ|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山